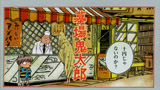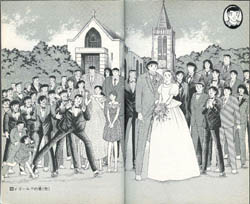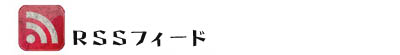みなさん、ある程度の時間、この人生というやっかいなものを過ごしていると、特定の名字に対してある種の固定観念みたいなものが生まれてきませんか?
たとえば、高橋という名字に私はある特定のイメージを持っています。
簡単に言えば「高橋姓にはなぜかバカが多い」というイメージです。
それは今まで出会ってきた高橋さん達の言動が私のなかで澱のように積もり、「高橋=バカ」という固定観念を生み出してしまったわけです。
もちろん、これは一般化できるような話ではなく、あくまで私の経験からくる局地的な真理でしかありません。(いや、真理ですらないですけど)
しかし、私が高橋という名字に「バカ」というイメージを持ってしまっているのは事実。
以下、試しに私の高橋という名字を持った人たちとどういう関わりをもってこうした結論に至ったのかについて簡単に書いてみます。
あらかじめ断っておきますが、全国の高橋さん、不快な思いをさせてしまってごめんなさい。
悪気は少ししかないので許してください。
小学校5年のときにクラスメートだった、高橋太郎くん。
高橋という部分は、そのままですが、太郎というのは仮名です。
さすがにフルネーム出すわけにはいかないので。
その高橋くんは、習字の時間に「好きな言葉を書け」というお題を出されて、こう書いた。

好きな言葉に「努力・友情・勝利」という、某少年誌のお題目を書いているところが、高橋くんがバカであることを示している・・・・・というわけではないです。
そんなことを言ったらジャンプ読者にケンカ売ってるようなもんですし。
実を言うとこの「努力・友情・勝利」は今、自分で適当に書いたものなので高橋くんとは何の関係もありません。
全体の紙の長さを考慮しなかったばっかりに、努力・友情のところは普通のサイズで書いているのに、勝利のところで紙幅が尽きてしまって尻すぼみになってるところがバカ!・・・・・・っていうわけでもありません。
今述べたように、これは自分で書いたものですし。適当に書いたら余白がなくなっちゃっただけです。(←バカ!!!)
実は高橋くんがバカであることを示すポイントはここ。

名前です。
高橋くん、自分の名字を間違えて、のぎへんにしてた・・・・・・・・・。そのとき、もう小5だったのに。
クラス中の爆笑をゲットした、この事件が私にはたいそう印象深く「ひょっとして高橋はみんなバカなんじゃないか」という疑念を抱かせるきっかけとなりました。
次に私が会った高橋さん。
この高橋さんは口から先に生まれたんじゃないかと思うほど、よく喋るオッサンでした。「お前と話しているとなぜか気が滅入る」と周りに評されるこの私を相手に2時間、3時間は平気で喋る。
よく喋れるな。私のような、ろくに相槌すら打たない木偶の坊相手に。
彼はどこがバカだったのでしょうかか?
この高橋さんは昭和18年生まれだったんですが、自分は「戦後生まれだ」と言っていました。
太平洋戦争の年表
1941年(昭和16年)
日本、英米蘭に宣戦布告(太平洋戦争開戦)
1942年(昭和19年)
ミッドウェー海戦
第一次ソロモン海戦
第二次ソロモン海戦
1943年(昭和18年)
山本五十六連合艦隊司令長官、ブーゲンビル島上空で戦死
イタリア、連合国に降伏。
東京で大東亜会議を開催、大東亜共同宣言を発表。
エジプト・カイロで英米中首脳会談(カイロ会談)
高橋さん、生まれる。←!!!
1944年(昭和19年)
グアム島の日本軍玉砕。
レイテ沖海戦
神風特別攻撃隊、レイテで初出撃。
米軍の新型爆撃機B-29、マリアナ諸島より東京を初空襲。
1945年(昭和20年)
クリミア半島ヤルタで英米ソ首脳会談(ヤルタ会談)。
硫黄島の戦い
東京大空襲
沖縄戦
戦艦大和沈没
ドイツ総統ヒトラー自殺。
ナチス・ドイツ滅亡。
米軍、広島に史上初の原子爆弾投下。
米軍、長崎に原爆投下。御前会議でポツダム宣言の受諾を決定。
8月15日 日本国民へ玉音放送(終戦の詔)。
年表を見ていただけると一目瞭然なんですが、高橋さん、どう見ても戦時中に生まれてます。
中学、高校生くらいが、終戦が昭和20年ということを知らないことには別に何も思いません。
昔の話だし、そう正確に覚えていなくても当然だろうとは思う。
そもそも、昭和で覚えるよりも、西暦1945年が終戦、という覚え方をしてる人のほうが多いでしょうし。
だけど、いくら終戦当時に物心がついてなかったとは言っても、戦前生まれの人間が終戦がいつかってのを知らないってのはどうも・・・・。
この高橋さんとの出会いが私のなかで「高橋=バカ」という図式を決定的なものにしました。
だから、私は高橋という名字の人と会ったりすると、それだけで「ひょっとしたら、この人ってバカなんじゃないか?」と思ってしまうクセがついちゃってます。
高橋陽一先生、ごめんなさい。
先生がサッカーのルールをガン無視した漫画描くのは、先生がバカなせいじゃないかとかひそかに疑ったりしてます。勝手な思い込みでホントにごめんなさい。
フィギュアスケートの高橋選手、ごめんなさい。
あなたがいつも、口を半開きにしてるのをテレビで見ていると私のなかで「高橋=バカ」説がより信憑性を帯びてきます。
せっかく、男前なんだから、もう少し口を閉じたほうがいいんじゃないでしょうか。老婆心ながら。
えっと、この高橋以外に印象深い名字というと「高原」ですかね。
つーか、また「高」の字がついてますが。
高橋さんと違って、私は高原さんを一人しか知らないんですが、この人があまりに強烈な人だったので、高原と聞くと、私の頭のなかにはすぐこの人のイメージがわいてきます。
この高原さんは、当時25くらいでしたかね。
見た目はちょっと怖かった。
で、この高原さん、車に乗っていて、妙齢の女性を見かけると、おもむろに窓を開け
「姉ちゃん、やらせろや!」と大声で叫ぶという、まあ、とんでもない人でした。
そのほかにも、背中に墨が入っていたり、ムショ帰りだったり、シャブ中だった過去を持っていたりすることもあって、それ以降、私のなかで「高原は野獣」というイメージを決定づけてくれました。
サッカーの高原選手とかも、優しそうな顔してるけど、さぞかし野獣なんだろうなー。まあ、何の根拠にもなってないんですけど。
と、このように人間というものは、特定の名字に対して何らかのイメージを持ってしまっていることが、ままあるんじゃないかと思われます。
それは、同じ名字に同じタイプの知り合いが何人かいるという、経験の蓄積からくる思い込みであったり、一人の強烈な人を知っているがために、その名字に固定的なイメージがついてしまったり。
アニメ、漫画、ゲームでは、今まで聞いたことのない名字のキャラってのがよく出てきます。
日常生活では、まず出会うことのないタイプの名字。
こういう変わった名字が使われることの理由の一つには、上述した固定観念の混入をさける目的があるのではないか。
つまり、一般的でありがちな名字を使ってしまうと、そのキャラのイメージに受け取り側の固定観念(高橋=バカみたいな)が付与されてしまう恐れがあるために、普通、出会うことのなさそうな名字を付けているんではないか、みたいなことをずいぶん前に書いた覚えがあります。
我ながら下らない考察だったんですけど、下らないことを書いてるのはいつものことなので、まあ、いいか。
ここでは、現実→フィクションという矢印を避けるために、こうした珍しい名字が使われているわけですが、これを裏返してみるとどうでしょうか。
つまり、フィクション→現実という事態が発生したとき、我々はいかなる精神作用を及ぼされてしまうのか、という問題です。
具体的に言うと、既に特定のキャライメージがついている名字の人と現実で出会ったとき、我々は必ずその人を歪んだ視線で見てしまうに相違ない。
神楽坂 椰子 沢近 遠坂 厳島 涼宮 花鳥これらの普段の生活では滅多に出会うことのない名字の数々。
しかし、もし万が一、これらの名字の人と現実で出会ってしまったとき、たとえ、それが顔のホクロから毛がにょろんと出ているような、むさくるしいオッサンであったとしても、
「え?ツンデレ?」
とか思ってしまい、ひょっとしたら自分にしか見せないか弱い部分があるんじゃないか、などとありえない妄想にふけり、その毛がにょろんのオッサンについときめいてしまう。
そんな事態が考えられます。
また、
高屋敷 鳴沢 涼宮 北条 遠野 朝霧これらの名字の人がたとえ、細木数子みたいな美少年以外のすべてに敵意をむき出しにするようなオバサンであったとしても、
「え?ひょっとして妹タイプ?」
とか思ってしまい、まるで小動物を見るような愛おしい感情が沸き起こり、細木数子とありえない過ちを犯してしまう。そんな事態が考えられないこともない。
これはその名字が珍しいものであればあるほど、こうした精神作用は強くなると考えられます。
たとえば、神楽坂、椰子、沢近、厳島、花鳥、高屋敷、鳴沢あたりは相当に珍しい。
なので、こうした名字の人と出会った時の精神作用、言い換えれば感激は相当に強くなってしまう可能性があります。
なので、特に注意が必要かと。
[参考記事]
属性別選手権 ツンデレ級王者決定戦第2回 属性別選手権 いもうと級ところで、この両方に出てくる涼宮という名字なんですけど、妹のほうの涼宮茜(君が望む永遠)のほかにも涼宮遥なんてのもいますね。つーか、それ茜の姉ちゃんなわけですけど。
ハルヒを想起すればツンデレ、茜を想起すれば妹、遥を想起すればなぜか涙がとめどなく溢れてくるという、この厄介な涼宮という名字。
しかし、この名字ってそもそも実在してるんですかね。
どうも、作り物臭いんですけど。
涼宮のほかにも、椰子とかもありえなさそうな名字に感じます。
しかし、椰子はかわいかったなー。もっとも、鉄(くろがね)のほうが好みではありましたけど。
あ、鉄(くろがね)もありえなさそうな名字だな、しかし。