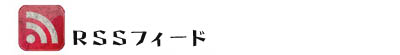今さらにもほどがあるんだけど、この本を読んでみた。
いやー、これ、とても面白かった。
2002年に庵野秀明と結婚した安野モヨコが夫婦の日常を描いたマンガ。
車に乗ればアニソン、特撮主題歌の入ったCDを延々かけ続ける、部屋はDVDとフィギュアで埋め尽くされてるという夫。
そのオタクっぷりに呆れつつも、次第に慣れ親しんでしまってる、というか慣れ親しまざるをえない妻ってのが妙におかしい。
抵抗してストレスをためるより、なじんだほうがラク・・・・ということに気づきました(車内で一緒にアニソン合唱しちゃったあとの安野の述懐)
このマンガのなかでは、庵野は「カントククン」というキャラとして描かれているんだけど、このカントククンのキャラがかわいい。
オタクであることに無邪気で、純真。
そこが、なんとも愛らしい。
たとえそれがキャラ化して描かれているものだとしても、まさか、庵野秀明という人物を「かわいい」などと思ってしまうことがありうるなんて思いもしなかったよ。
もちろん、夫婦なんてのは、どれだけ仲がよかったにしても、各種のいざこざがあったりするもんだし、この本のなかで描かれているのは、夫婦生活の一面を極大解釈してみせたものだくらいはわかっている。
生々しい現実をフィクションとして昇華させるために、二人がキャラとして描かれているんだろうし。
しかし、そんなところでの読みとりかたはどうでもよくて、実際、私はこの夫婦にとても好感をもっちゃった。
嫁さんは巷ではすごく気丈な女性というイメージが大きいとは思いますが、本当のウチの嫁さんは、ものすごく繊細で脆く弱い女性なんですよ。つらい過去の呪縛と常に向き合わなきゃいけないし、家族を養わなきゃいけない現実から逃げ出す事もできなかった。ゆえに「強さ」という鎧を心の表層にまとわなければならなかっただけなんです。心の中心では、孤独感や疎外感と戦いながら、毎日ギリギリのところで精神のバランスを取っていると感じます。だからこそ、自分の持てる仕事以外の時間は全て嫁さんに費やしたい。そのために結婚もしたし、全力で守りたいですね、この先もずっとです。(巻末の庵野秀明のインタビュー)
人ののろけ話はあまり聞きたくはないもんだけど、なぜか許せるのが不思議。
ところで、この本のなかに庵野秀明は風呂に入らないというエピソードが出てくる。
なにしろ自分のアパートの風呂は壊れて使えなかった、カントクくん
銭湯には週1,2回・・・・・(行けばいいほう)
洗たくなどはするわけもなく
洋服もボロくなるまでずっと着て、汚れたら捨てていた
つき合いはじめの頃、カントクくんの部屋を片づけていたら「捨てた」パンツがゴミ袋4個分あった・・・・
これを読んで、ニルヴァーナのカート・コバーンも風呂に入らなかったっていうエピソードを思い出した。
1ヶ月に1回しか風呂に入らず、毎日風呂に入る奴をバカにしてた、っていうカートのことを思い出した。
不潔な人間が清潔な人間を見下す、という心理があることを、私はカート・コバーンの件で初めて知り、驚いたもんだ。
どうもキリスト教には「体を清潔にしているのは異性を誘惑していることだ」みたいな感覚が昔あったらしく、そこから隔世遺伝みたいな形で受け継がれていったもんかもしれない。
まあ、これは単なる思いつきで、何の根拠もないんだけど。
いきなり、ニルヴァーナの話なんかしちゃうと読んでいる人は面くらうのかもしれないけど、私にとってはそれなりに合理的な筋道なのだ、これ。
自分のなかでは、ニルヴァーナとエヴァって、実はとても近しい存在で、90年代の文化というと、この二つが即座に思いうかんでくる。
私の脳内地図の上では、ナデシコやウテナやカウボーイ・ビバップよりも、ニルヴァーナのほうがずっとエヴァに近い。
この二つは、アニメと音楽という表現方法の差こそあれど、その底のところではかなりの部分で共通している。
まず、陰鬱な内面描写が多いってのがそうだけど、それだけじゃなく、その表出のさせかたがとても似通ってる。
カート自身は「強弱法」っていう呼び方をしてたけど、ニルヴァーナの音楽はゆったりとした静かなパートと絶叫を伴った大音響のパートがかなり明確にわかれてる。
内へ内へ螺旋を描いていったものが、一挙に放出されるイメージ。
エヴァも同じで、陰鬱な内面描写がえんえん繰り返された後、シンジが絶叫しながら暴力をふるう。
外部に追いつめられた内面が、ある臨界点を越えると一気に外部への暴力性として表出されるっていう表現スタイル。
そこがこの両者に共通しているところだ。
国も背景としている文化も、構成しているものだけを見れば、毛ほどもかぶってるようには思えないけど、私はこの二つの表現を似たようなもんだとずっと感じてた。
こんなわけで、この本を読んでいたら、ニルヴァーナのことを唐突に思い出してしまったので、久しぶりにカート・コバーンの伝記を読み直してみた。
最初に大ざっぱな印象から述べると、とても痛々しかった。
もう、カート・コバーンという、このロックスターにあこがれることのできる年齢でもないし、ただ読んだ印象をそのままに受け止めてみたんだけど、それはやっぱり痛々しいとしかいうことのできないものだ。
かつては林業で栄えたものの、今は何の娯楽もない田舎町で育った人づきあいの極端に苦手な青年。
人と会話することに何の楽しみも見いだせず「それなら寝ているほうがずっといい」とすら言うカート。
そんな彼が、クリスとデイヴというバンドメンバーを得て、世界的なロックスターになっていく。
だが、それは成功というよりも、前からかかえていた混沌をさらに加速させるものでしかない。
「服用すれば胃痛が消えるから」と言い訳しながら、結婚したコートニーといっしょにヘロインにおぼれる。
カート自身は、ヘロインをやってるのは耐えがたい胃痛のせいだと語ってはいる。
なにせ他人の体のことだから何とも言えないが、とにかくヘロイン服用はカートとコートニーをこんな状態にした。
「ホテルの部屋に入ったときに、こいつらは本当にひどいことになってるとわかったよ」とデイヴは言う。
「二人はベッドの上にボロボロ状態でぶっ倒れていた。気分の悪い悲惨な光景だった。彼らに怒りは感じなかったけど、彼らがこんなことをしなくちゃいけないほど悲惨な状態にあることに怒りを感じた。自分の体が機能しなくなるまで、よだれをたらす赤ん坊のようになるまで、あんなことをする人がいるなんて痛ましいよ。『よし、ドラッグをやってメチャクチャになって醜態をさらそうぜ』って感じだろ。あそこまでやるのはバカげているし、悲惨だよ」。
「カートの部屋を訪ねたら、下着一枚のカートがドアを開けてくれた。ベッド・カヴァーからコートニーの髪の毛が少し覗いてた」とウェンディは言う。「古くなった食べ物のトレーが5つほど、ワゴンに乗ってたから、『カート、どうしてメイドさんを呼ばないの?』と尋ねると、コートニーが『ダメなの。彼の下着を盗んじゃうから』と答えたわ」。
これだけ読むと、ジミ・ヘン、ジャニス、シド・ビシャスといった、かつてのロックスターの歩んできた道をそのまま、なぞっているかのように見える。
そして、カートがありきたりなロックスターであったのも、また事実だろう。
たとえば、ヘロインをやってみたのは、イギー・ポップにあこがれていたから、という下りがこの本のなかにある。
少なくとも、あこがれのロックスターの姿を反復してしまう程度には、カートは弱かったし、また平凡な人間だった。
そういう平凡さというのが、今回、読み直してみてやたらと目に付いた。
たとえば、バンドが有名になったとたんに、カートが自分の著作権料を増やすように、他のバンドメンバーに要求するくだりがあるんだけど、これなんかもそうだ。
なんて、ありきたりな話だろう。
この伝記は、カートを神格化しようとはしていない。むしろ、その逆で彼がいかに普通の人間であるかを書こうとしている。
ただ、カートは普通の人間よりも致命的に弱かった。それが、あの悲劇的な結末の原因だろう。
ところで、今回この伝記を読み直してとても興味深く感じたのは、カートが性差別主義者、体育会系、ヘヴィメタルといった、自分たちの文化(パンク、グランジ)以外の文化集団に対して、激しく反発しているってことだ。
(嫌っていたパール・ジャムのメンバーであるジェフ・アメンがバスケット・ボールの州代表であったことに対して)
「体育会系の奴らが音楽業界にまではびこってる。最近は筋肉モリモリのマーキー・マークみたいな奴ばっかりじゃないか。ゾッとするよ。あいつらに仕返しするために、僕もバスケをやり始めるつもりだよ」
こんな感じでカートは他の集団に対する敵意をむきだしにしている。
この本のなかには、他にもこうした呪詛が満ちあふれている。
性差別主義者に対する敵意というのは理解できるけど、体育会系やヘビメタなんて、そんなに敵視するほどのものなのか、って疑問に思う。
まあ、ヘビメタとパンクは昔から仲が悪いと相場が決まってるもんではあるけど。
なぜ、カートはどうでもよいものに対し、必死に毒づくのか。
まるで、何かを否定しつづけていなければ、自分を保てないみたいに見える。
こういう露骨な敵意というのは、エヴァ当時の庵野にも見られたものだけど、庵野の場合は敵意を向けた先が「オタク」という、自分が所属してる集団であるところが決定的に異なってる。
この差が出てくる一つには日本とアメリカの違いだろう。アメリカのほうが、異なる文化間での対立が直接的だし、またときに暴力的だから。そこでは、自分を守ることで精一杯で、自己批判をしてるゆとりなんて、なかなかないんだろう。
それともう一つ、外部と対立することを前提としたロックと、外部を無視して内にこもることを前提としたオタクの違いもあるのかもしれない。
それはともかく、オタク批判、つまりは自分自身を批判し続けた庵野秀明は、それから10年後、嫁さんに自分を笑えるキャラとして描かせるようになった。
いっぽう、他者を敵視しつづけたカート・コバーンは「だんだん消えていくくらいなら、一気に燃え尽きた方がマシだ」と遺書を書き、自分の頭を銃でブチ抜いた。
たしかにエヴァ以降の庵野というのはみっともなかったのかもしれない。
迷走してた感がありありだ。
また、カートの自殺というものも、私は倫理的に非難することはできない。
この生が生きるに値するのかどうか、そんなことは知らないし、また興味もないから。
だけど、どっちの生き方が好きかと問われれば、庵野のほうかなってことくらいは言える。
エヴァ以降の10年というのは、庵野が自分のカリスマ性を失墜させていく過程だったが、それはそれでいいじゃないか。
結局、人の期待したカリスマ性なんてものに応えなきゃいけない義理なんてどこにもないのだ。
いっぽう、カートは自殺することで、ロックのカリスマになった。つーか、なってしまった。
しかし、そんなカリスマだとか何だとか、そんなものがいったいなんだっていうのだろう。
ただ、彼は普通の人間よりも、弱かっただけのことだ。肉体的にも精神的にも。
そこに同情はするし、また共感しちゃったりもする。実際、ネヴァーマインドを久しぶりに聞き返してたら、泣きそうになったし。
しかし、思いっきりドライに言ってしまえば、彼は悲しいまでに弱かった、ただそれだけのことだ。
そこに感傷の甘い粉をまぶして神棚にそなえるのも勝手だろうが、とりあえず私はそれに興味がない。
一つ勝手な夢想をすることを許してもらえるなら、もしカートが日本に生まれてオタクにでもなっていれば、もう少し楽に生きられたんじゃないか、って思いもした。
[参考記事]
安野モヨコ「監督不行届」 Trick×Trickエヴァじゃなくて"庵野"について書くよ-Trick×Trick